ブログ

【資金繰り】節税策は基本的に余分にお金を使うか納税時期を遅らせるかの2択
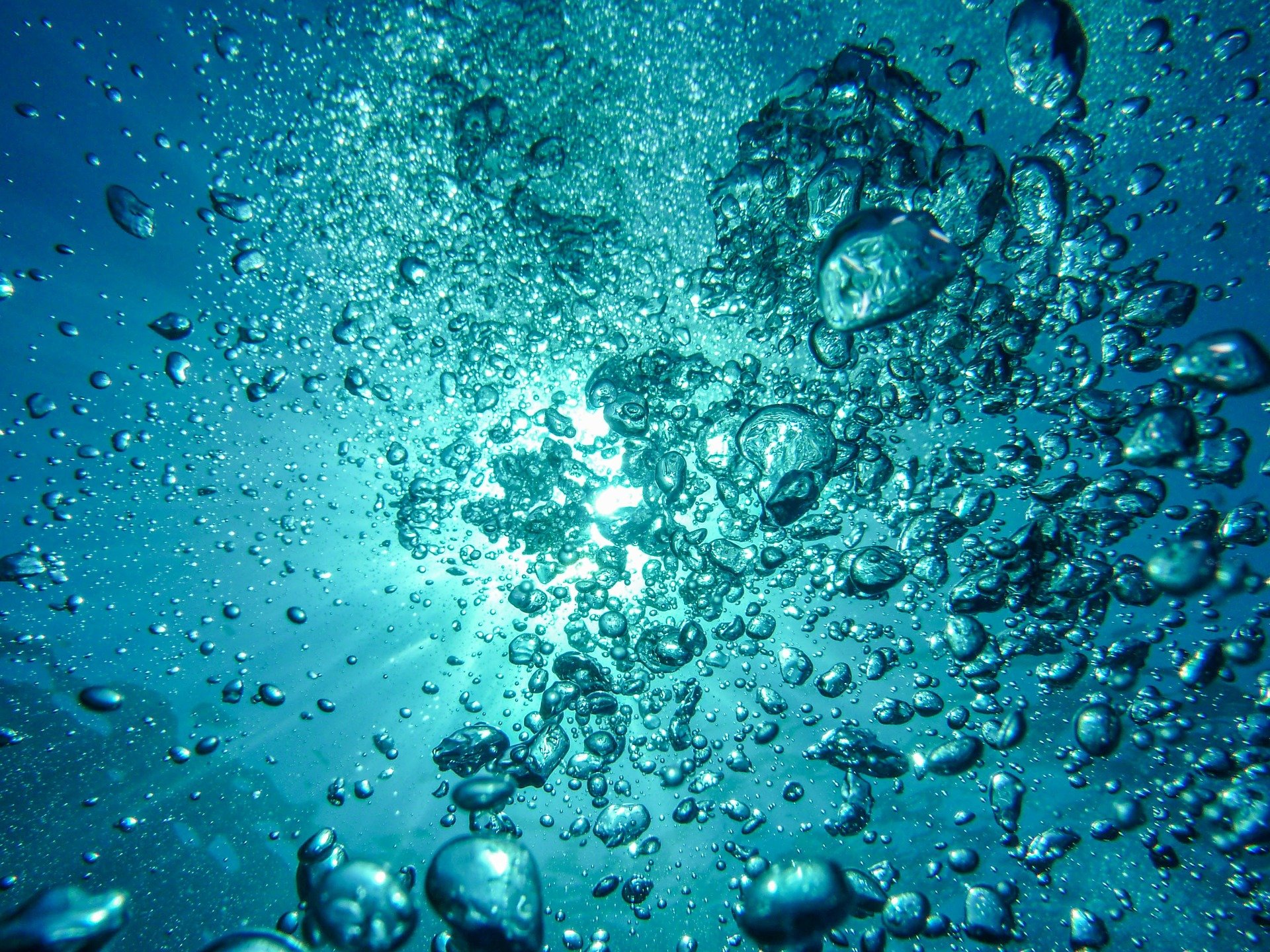
経営者の方によく「節税方法はどんなのがあるの?」と聞かれます。
自分でも節税策がないのかと思うので、経営者の方の気持ちはわかります。
そこで友人の税理士に「利益が出そうやけど、何か税金抑える方法とかあるの?」と聞いてしまいます。
ですが決まって回答されるのが
「節税策は、余分にお金を使うか支払いを遅らせるかの2択やで」
となります。
普段から帳簿を付けている人にとってはすぐにできることですが、今年の帳簿を全くつけていない人は、決算期が残り3か月くらいになれば、そろそろ今年の利益がいくらになりそうなのかを予想してみましょう。
思いのほか利益が出ている場合は、何かしらの節税策を行いたくなるものです。
早めに確認できれば、それだけ打ち手も増えます。
では節税策には、“余分にお金を使うか支払いを遅らせるかの2択”とはいったどういうことでしょうか?
税金の計算方法を簡単に知っておく
※注:一般的な税金の事を書いていますが、税金のことは必ず税理士にご確認ください。
まず、個人事業主にかかる税金は「所得税」「住民税」「個人事業税」がその年の利益に応じてかかります。
他には売上と支払った額に応じて「消費税」がかかり、他には「固定資産税」や「自動車税」など所有に応じて発生するものもあります。
ここでは、節税策をその年の利益に応じてかかる「所得税」「住民税」「個人事業税」について考えてみます。
所得金額と所得控除
税金の計算をするのに、計算された利益額にそのまま税率がかけられるのではなく、そこから様々な「所得控除」額を引いて計算されます。
税金の計算をする際に、利益に対して直接かかるものでなく、利益が出た後に「所得控除」と呼ばれるものを差引いたものを「所得金額」と言います。
基礎控除や生命保険料控除、寄付金控除(ふるさと納税)などがあります。
所得税の計算方法
「所得税」とは、個人の年間所得額に応じて支払う税金で、国に納めます。
所得税は累進課税制度のため、たくさん稼いでいる人ほど高い税率がかけられ、税率は5%~45%となっています。
所得金額に応じて決められた税率をかけ、そこから控除額を引いた金額が所得税となります。ここで出た控除額は計算された税金から直接差し引かれますので、所得控除とは別になります。
所得税の計算は
所得金額×税率-控除額
となります。
住民税の計算方法
「住民税」とは、こちらも個人の年間所得額に応じて支払う税金ですが、こちらは住んでいる都道府県と市町村に納めます。
所得税と住民税は、成人している国民全員が対象で、税率は都道府県+市町村=10%、と基本的に全国同一です。
税金の計算は
所得金額×税率
となります。
個人事業税の計算方法
「個人事業税」とは、事業を行っている70の法定業種を営んでいる個人事業主に課せられる税金で、都道府県に納めます。
税率は業種によって異なり、3%~5%です。
個人事業税は事業所得金額が290万円以下の場合はかかりません。
所得税や住民税と違い、こちらは事業所得(事業から出た利益)のみにかかります。
税額の計算は
(所得金額-事業主控除額290万円)×税率
となります。
納める税金
税金の計算は簡単に言えば
売上-経費-控除=所得金額
所得金額×税率=納める税金
となります。
個人事業主の税金計算例
所得金額によって所得税の税率は変わりますが、例えば事業所得が550万円、その後所得控除を差し引いた所得金額が400万円の個人事業主であるAさんの場合、ざっくりとした税金は
所得税 (所得金額400万円×所得税20%)-42.7万円=37.3万円
住民税 所得金額400万円×住民税10%=40万円
事業所得 (550万円-290万円)×個人事業税5%=13万円
合計37.3万円+40万円+13万円=90.3万円
になります。
すごくざっくりと言えば、Aさんは90.3万円÷400万円=22.6%と、所得金額の22.6%の税金を納めることになります。
納める税金を少なくする方法
税金の計算は簡単に言えば
売上-経費-控除=所得金額
所得金額×税率=納める税金
となりますが、納める税金を少なくするにはどうすればよいのでしょうか。
計算式を見れば、
①売上を下げる
②経費を上げる(費用を増やす)
③控除額を増やす
となります。
一見複雑そうな話ですが理屈とすればとても単純な話で、税金を下げるには所得金額を減らすことであり、上記の①~③しかありません。
脱税となる3つの方法
売上をごまかして下げる
しかし、①売上を下げる、は意図的な利益操作になりますので“脱税”となります。
経費を水増しする
②の経費を上げるも、支払ってもいない架空の経費を計上することとなるので“脱税”です。
在庫を減らして申告する
在庫のある業種の場合、在庫金額を実態より少なく申告すれば、その分だけ利益が減ります。
売上原価の求め方は、
期首棚卸高+仕入-期末棚卸高=原価
となるので、差し引く期末棚卸高を少なくすれば、それだけ原価が増えることになります。
もちろん“脱税”に当たります。
ちなみに在庫を多くすると、その分利益が増えますが、その行為は“粉飾”となります。
節税策は余分にお金を使うか納税時期を遅らせるかの2択
脱税となる行為を避け、納税額を減らす方法は
①実際にお金を使う
②今年の納税額を将来に先送りする
となります。
実際にお金を使って利益を減らす
実際に事業に必要なものを購入することやサービスを受けることで、利益を減らすこととなり、最終的に納税額が減ることとなります。
上記のAさんの場合、ざっくり言えば所得金額の22%くらいが税金でしたので、仮に100万円追加で経費を使うと
100万円×22%=22万円
と、22万円納税額が少なくなります。
実際にお金を使って利益を減らす場合の注意点
この追加で使った100万円が本当に必要な場合は何も問題は無いです。
しかし、単なる無駄遣いになるようなものであれば、税金を22万円少なくするために、余分に78万円のお金を支出したことになります。
また、来期以降の費用を前払いで使ったものに対しては、今期の費用と見なされませんので注意が必要です。
お金は将来への投資となるように使う
前払いで払うものに対しては注意が必要となりますが、今期にモノが手に入る、サービスを受けるものであれば大丈夫です。
税金を少なくするために使う経費なので、通常の事業経費以外に使うことになると思いますので、その使い道は“投資”となるようにするのが望ましいと考えます。
例えば、古くなったパソコンを買い替える、従業員にセミナーや研修を受けてもらう、広告宣伝を行う、などです。
パソコンなどの買い替えは、処理能力が向上するので日々の生産性向上につながります。
人材の育成は、サービスを今受けますが、その効果が表れるのが先になります。
広告宣伝も、認知度向上などを狙ったものであれば、その効果はすぐにはでません。
仮に効果がすぐに出て利益が増えると納める税金額は増えますがその分利益額も増えます。
事業を営む本来の目的が達成されるので、それはそれで好ましい事と考えます。
少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
ちなみにパソコンなどの購入は本来であれば固定資産なので、決められた年数ごとに減価償却費を計上(経費を計上)することになりますが、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例」では、取得価格が30万円未満であれば1年で償却することができます。
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
(国税庁HPより)
※詳しくは税務署か税理士に確認ください
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 国税庁HP
納税額を将来に先送りする
納税額を将来に先送りするとは、
「経費を今期に計上するが、将来利益として戻って来る」
ことです。
よく保険の営業マンが「節税対策に使えますよ」みたいな商品を勧めてきますが、
実際には「今期の節税に使えますよ。将来解約して利益が出るときには、何らかの経費を計上すれば問題ないですよ。」といったものです。
決して税金が少なくなある訳ではないことに注意しましょう。
事業を営むのに絶対は無く、天災やコロナウイルスのように行動様式が変わって収益が急速に悪化する場合もあります。
そのような時、かけていた保険金を解約して損失補填に充てることで、いま支払う税金を将来の損失と相殺することで、トータルとして納税額を減らすことになります。
近年ではこのような保険商品を使った納税の先送りに対して、国税庁も問題視しています。
保険商品を巡る課税上の諸問題-支払保険料の損金性の問題を中心に- 国税庁HP
保険商品を使うことが問題でなく、経営者が突然亡くなることも可能性としてはゼロではないので、純粋に保険をかける目的に合致しておけば問題は無いと言えます。
あくまで、節税目的で保険をかけたが、むしろ資金繰りが悪化する、いま解約すれば損をする、解約時に損失を充てるつもりが予定通りうまくできなかった、などが生じた場合に問題となります。
保険を使った手法以外もありますが、基本的には「納税の先送り」になります。
小規模企業共済
将来へ納税を先送りするに違いないですが、個人事業主や小規模事業者であれば、小規模企業共済が最もいい仕組みかと思います。
小規模企業共済とは、国の機関である中小機構が運営する退職金制度で、全額所得控除されます。(所得控除なので経費扱いではない点に注意)
また、受け取り方法によって異なりますが、退職所得扱いになれば所得控除額が大きいため、その分納税額が抑えられます。
国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約153万人*の方が加入されています。掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。
(中小機構HPより)
また、積立額に応じて低利で融資を受けることも可能なため(掛けていた金額を担保)、急な資金繰り悪化などに対しても対応可能となります。
個人事業主や小規模事業者の退職金積立を主目的としながら節税に使え、国の機関が運営している安心感もあるので、節税策を講じていない事業者の方にはお勧めしています。
税金だけでなく社会保険にも注意
利益が出ればすぐに「税金が高くなる」と考えて節税策を探しますが、実際には社会保険の負担額にも注意が必要です。
国民健康保険の場合、むしろ税金よりも国民健康保険料の方が、インパクトが大きいです。
国民健康保険は住んでいる自治体によって金額が異なりますし、計算方法が複雑なので、自治体の窓口で確認ください。
ちなみに私が住んでいる神戸市は全国でもトップクラスに国民健康保険が高く、一番安い自治体との差が年間約30万円(年収400万円の場合)もあるそうです。
よく「法人成りするにはどれくらい利益が出た時が良いですか?」と聞かれますが、税金や社会保険の面からでいれば、それは国民健康保険を支払うのが良いのか、法人化して税金の支払い額は増えるかもしれないけど、社会保険料を抑えてトータルで安くなる方がいい方で考えることになります。
一応返答としては
「すごくざっくり言えば利益が400~500万円くらいでだしたら考えるのが良いようです」
と答えています。
ですが法人成りの効果は他にもあります。
ひとつは「信用」(本来であればこちらの方が重要かも)の部分が個人事業主より高くなります。
融資も個人保証(代表者の保証)が無ければ、法人と個人とを別けることができます。
万が一事業がうまくいかなくなり融資の返済ができなくなっても、個人は自己破産等を免れます。
他には家族を従業員扱いにできる、等があります。
一方でデメリットもあります。
まず赤字でも均等割りと呼ばれる最低限の税金を支払う必要があります。
また、経営者の給与も勝手に変更できません。(勝手に変更しても、税金計算の段階で考慮されます)
色々と法人化することのメリットデメリットがありますので、一概に「○○円になったら法人化が良い」とは言えないものです。
まとめ
友人の税理士は
「節税節税と言っている社長より、税金を払っている会社の方が事業は伸びてる感じがするなぁ」
とも言ってました。
統計を取っている訳でもなく、あくまでも友人の感覚なのですが、25年も税理士業界で生きてきているので、その感覚も遠からず当たっているのかなぁと思いながら聞いてます。
結局のところ、節税の抜け道をアレコレ探すのに時間をかけるより、事業の継続発展に注力しているほうが良いって事かもしれません。
ただ、使える制度を使って将来へ備え、結果として節税につながる事は悪い事ではないです。
節税策には、“余分にお金を使うか支払いを遅らせるかの2択”と考え、将来へ投資をしたり備えたりすることで上手に節税につながれば、それで十分なのではないかと思います。

中小企業診断士/ファイナンシャルプランナー/全経簿記上級
中小企業3社(食品製造・アパレル)で約20年間財務経理部門を担当。2017年に中小企業診断士として独立。2020年株式会社ノーティカル設立。
事業計画・資金計画の立案から金融機関折衝や資金調達、計画実行支援を中心に、経営改善や新規事業支援を行う。
-

-

-

お問い合わせ
Contact
- Webでのお問い合わせはこちら
- お問い合わせフォーム 24時間年中受付中